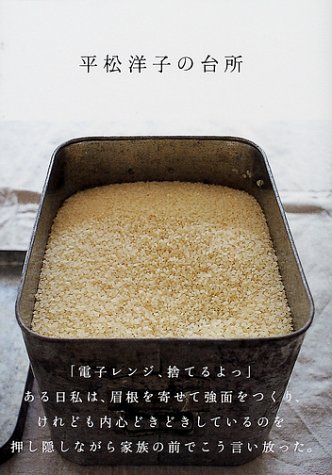「彼女の書く文章がリアルタイムで読みたかった」と私が心から思う「彼女」というのは、須賀敦子さんのことである。
この『須賀敦子のローマ』は、須賀さんとも親交のあった大竹昭子さんが、須賀さんの書いたローマについての文章と、その場所を写真におさめている。ミラノ、ヴェネツィアのあとの3冊目として書かれ、今年3月、『須賀敦子の旅路 ミラノ・ヴェネツィア・ローマ、そして東京』として文庫化された。
須賀さんの書いた本の中で、断片的に綴られたローマの文章で、どこかで読んだのに、タイトルは思い出せずに、あとから見つけられないということが私は割と多い。なんとなくまた読みたいのに見つからなかったローマについての文章がまとめられていて、とても嬉しい。
ローマについては、須賀さんがフランスの留学から戻って、再度、踏みだした最初の地という印象がある。ローマの最初の学生寮は合わなくて、次にテルミニ駅の近くの寮に移って過ごした日々があり、その後も何度となく、友を訪ねたり、再訪した地である。
「アヴェンティーノの丘というのは、いうまでもなく、いわゆるローマの七つの丘の一つですが、他の丘にくらべ、比較的昔のままの静かな雰囲気の残っている、朝のひかりの清々しい高台です。アヴェンティーノの丘に行くなら、朝でなければ、と、ローマっ子のいうのも、いってみればすぐうなずけます。前にいった、サンタ・サビナの横の公園の見晴らし台から、テヴェレ川をへだてて、朝の陽光のなか、ずっと遠くに、しずかに息づいている、サンピエトロの白い大理石の円屋根にいたる甍の波を見る度に、この永遠の気高さに、その豊かな美しさに、思わず手をうって喜びのこえをあげたくなるのは、私だけでしょうか」
(全集第八巻『聖心の使徒』「ローマの聖週間」)
この文章を読むだけで、陽光に輝く対岸の様子が浮かんでくるよう。アヴェンティーノの丘には、マルタ騎士団の館やいくつかの教会がある。須賀さんはサンタンセルモ教会に通っていたという。
ローマは私にとっても、何度行っても飽きることがなく、少し行かないでいると、また恋しくなってしまう場所である。
地図を見ながら、次に行くときには、アヴェンティーノの丘にあるホテルに泊まって、朝、テヴェレ河と対岸を望む高台に立って、思い切り、朝のひかりを浴びてみようと思う。観光客が来る前に、騎士団の館近くの「鍵穴」を覗いて、サンピエトロ大聖堂を見てみようと思う。
東京 : 河出書房新書 , 2002
121cm ; 150p
須賀敦子の旅路 ; ミラノ・ヴェネツィア・ローマ、そして東京
/ 大竹 昭子著
東京 : 文春文庫 , 2018
16㎝ ; 487p