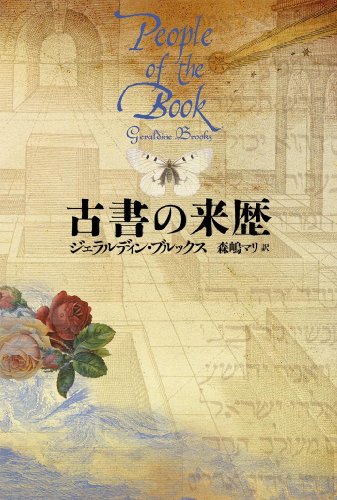フローベール著の「ボヴァリー夫人」を読んで、数年たってから、水村美苗さんの新聞小説「母の遺産」で、フランスへ留学していた学生時代に、夫とパリで出会い恋に落ち結婚した主人公が、夫の浮気や母の介護などに遭遇していく小説の中で、この”ボヴァリズム”という言葉が出てきたと記憶している。漠然と意味はわかっていたが、コトバンクで検索してみると、以下のように出ている。
デジタル大辞泉の解説
ボバリスム(〈フランス〉bovarysme)
《「ボバリズム」とも》フランスの作家フロベールの小説「ボバリー夫人」の主人公のように、現実と夢との不釣り合いから幻影を抱く精神状態。
あー、なるほど。と、思う方も多いのではないかと思う。
新潮社で出された生島遼一氏訳のものを読んでから、姫野カオルコさんの書いた絵本の「ボヴァリー夫人」を読んだが、どちらも同じ話なのに、切り口を変えて楽しめた。
絵本のほうから、簡単にあらすじを書くと、
184X年のフランス。のちにボヴァリー夫人になるエマは女子だけの寄宿舎で学校生活を終え、温和で免許医になったシャルルと結婚した。結婚生活は田舎の町トストで始まった。ボヴァリー夫人は田舎での退屈な生活と、冴えない夫を愛すことができずに、辟易しながら毎日を過ごしていた。
ボヴァリー夫人は妊娠した。夫のシャルルは妻の気持ちが晴れるようにトストよりも少し町であるヨンヴィルに引っ越した。そこでボヴァリー夫人は丘の上で一人で読書したり、ドイツ音楽に胸打たれる孤独な青年レオンと出会った。彼も彼女に憧れた。レオンは彼女にとって「絵や詩や音楽について話せる異性」だった。ヨンヴィルの町も、彼と並んで歩いただけで不道徳とされる地方の町だった。レオンは法律事務所で修行するとパリに旅立った。
そんなときに、夫のところに急患で運ばれた男の主人である町外れの大邸宅に住むロドルフ・ブーランジェと出会う。遊び人ともっぱらの噂の男。舞踏会の日に彼はボヴァリー夫人を誘惑した。ロドルフには簡単なことだった。ボヴァリー夫人とロドルフは逢瀬を重ねた。
ボヴァリー夫人は本気で彼を愛し、逃避行を提案した。ロドルフは厄介なことになったと思っていた。逃避行の当日、彼女はロドルフからの長い手紙を受け取った。彼は彼女と逃避行しなかった。ボヴァリー夫人は失意の中にいた。
夫のシャルルはふさぎ込む妻を心配し、彼は興味のないオペラであるが、ルーアンまで妻を連れ出した。そこでレオンと再会した。レオンはパリで洗練されていた。あっという間に火がついた。ボヴァリー夫人はピアノを習いに行くといい、ルーアンに毎週出かけ、レオンと愛を確認しあった。
しかし現実が待っていた。ボヴァリー夫人は人妻で、シャルルが相続した遺産を抵当にいれてまで浪費を繰り返していた。夫のシャルルは鈍感にも自分を許すだろうとボヴァリー夫人は思ったが、薬剤師の家に忍び込み毒薬を飲んで、自ら命を絶った。
それでも夫は妻を愛し、亡骸にすがって泣いた。半年後に彼も亡くなった。
こんな話だった。最後にこんなセリフがある。
わたしはただ境遇に身をまかせ、
境遇の波に自分の夢をさらわれてしまった。
失うだけの人生だった。
自分で拓くことなど何もせず。
この小説に出てくる主人公エマが、はじめに夫と住んだ町がルーアン近郊のトスト(tostes)の町、その後引っ越したのがヨンヴィルという町だった。小さな町からみれば都会であるルーアンの町にも時々出かけている。出かけるにしても駅馬車を使う時代。ヨンヴィルは見つけられなかったが、トストという町はルーアンから南に約30kmの場所だった。
本を読みながら、ルーアンの町は行ったことがあるので、イメージできたが、その時代の近郊の田舎町とはどんなところなんだろうと思って読んでいた。
本を読んでから少しして、フランスのオーガナイザーのツアーを頼まれて作っていた時に、リヨン・ラ・フォレという町を入れたことがあった。「ボヴァリー夫人」の映画が撮影されたとそのとき知った。写真を見る限りでは、私のイメージした通りの町だったので、なんとなく嬉しくなった。地図で見ると、リヨン・ラ・フォレはルーアンの東に約40kmの場所。
映画で「ボヴァリー夫人」は何作も作られたようだが、【AGIJ】フランス日本語ガイド通訳協会の公式サイトを読むと、このリヨン・ラ・フォレは「第2次大戦前には映画監督のジャン・ルノワールが、1990年にはクロード・シャブロールが監督した2作の<ボヴァリー夫人>の撮影が行われた場所」だそうだ。
小説から話が離れるようでもあるが、リヨン・ラ・フォレは「フランスの最も美しい村」の認定を受けている。
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org
小説に書かれている本当の舞台に行くのもいいけれど、さらに展開して映画からインスピレーションを受けた地に行くのも悪くないかも。旅は自由自在だから。
ボヴァリー夫人 / ギュスターヴ・フローベール著 ; 芳川 泰久 訳
東京 : 新潮社 , 2015 , 660p ; 16㎝
英文書名: Madame Bovary
著者原綴: Gustave Flaubert
ボヴァリー夫人 / ギュスターヴ・フローベール[著] ; 姫野 カオルコ[文]
; 木村 タカヒロ [イラスト] - 東京 : 角川文庫 , 2003 ; 19㎝
母の遺産 : 新聞小説 / 水村 美苗[著]
東京 : 中央公論新社 , 2012 ー 524p ; 20㎝